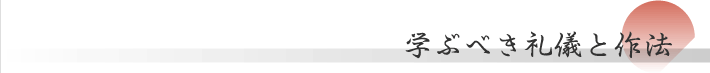|
1
|
一切を無にし、白紙にせよ。「素直」こそ、内弟子の研究心の原動力である。
過去に、何処で、誰に学び、どんな経歴を持っているか、そうしたものは一切問題にしない。素直さを要求される内弟子修行に、そうしたものは“無用の長物”である。心を常に白紙にリセットして、無から有を作り出せ。
|
|
2
|
何事も「自前主義」が大事。他人の世話にならないことだ。
20歳を過ぎたら、母親から乳離して「自立更生」の意識を明確にさせる。立命の精神は、自分の足で立つことだ。
また、「自前主義」を常に心掛ける。人に頼られても、人に頼るな。人に貸しを作っても、人に貸しを作るな。陵武学舍では、「自分の足で立つ根本精神」を教える。
|
|
3
|
不文律の大事。伝統に基づく「不文律」を弁(わきま)える。稽古事は、権威主義で構築されていることを忘れるな。道統の伝統ある権威を穢(けが)してはならない。
それは、自分の信じるものを穢していることに他ならず、結局、自分自身を無意識に穢していることになる。
|
|
4
|
厳格なる礼儀作法を弁えよ。
その為には、無断で人に背後に回り込むな。無断で人の室内に侵入するな。寝ている人間の頭部に近付くな。万一こうした場合は、人から自分が敵と思われる。これらは、「やってはならない禁忌」だ。目的から反れる事柄だ。
また、目上の者が坐っているのに、自分だけ立つな。目上と話す時に、躰を揺すったり、腕を組んだり、腰に手を当てて話すな。こうした事は、悪気がなくても「横着」と思われる。
何事も「断る」ことの大事を知れ。頭を低くして「謙虚」を学べ。
人から「あいつは虫の好かん奴だ」と思われて、誤解を受けるのは、まだ自分の礼儀の「至らなさ」を引き摺っているのである。頭(ず)が高いのである。早急に改善すべし。
そして、その人の礼儀正しさと、頭の低さが、そのまま人格を作り、品格を作り上げているのである。品位のない人間ほど、軽蔑の対象になるものだ。
|
|
5
|
分際意識を知る。
内弟子は「内弟子の分際で」という、分際意識を持つことが大事で得ある。分際意識を持つと、素直に、謙虚に、頭を低くして、他人から誤解を受けずに人生を過ごすことが出来る。その上、分際を知る者は、人から信用を受けることが多くなる。
「人から信用される」ということは、実に大変なことであるが、分際意識を持てば、「慎み深い人間」という評価がつき、これにより信用を勝ち取ることが出来る。
内弟子は、決して奢(おご)ってはならない。目上の人間だけではなく、同輩や、後輩にも、こうした意識を持つだけで、「頭が低くて、頼れる人間」と信頼が抱かれる。
人生の勝利者になる為には、分際意識を知ると同時に、「頭を低くする」ことを学ぶべきである。 |
|
6
|
見送り・出迎え・行き先の告知の大事。
祖父母、父母、あるいは自分の師匠筋に当たる人に対しては、見送り、また帰宅や帰館の場合、出迎えるのが基本である。
往時の武人は目上が出かける時は「いってらっしゃいませ」と見送りの挨拶をし、帰館した時は「お帰りなさいませ」と挨拶をしたものである。
また、行き先は必ず伝達し、更に予定時刻より早くなったり遅くなったりする時は、その旨を出先から連絡するのが礼儀である。更に、遠方から訪問する時は、その旨を予め告知しておき、その告知当日には、到着予定を出先から伝えると云うのが礼儀である。 |
|
7
|
理不尽な暴力に出会った場愛の対処法。
暴力に対処しようとして、腕力を用いる前に、頭を使え。自分の吐く、「言葉」を武器として使え。しかし、この言葉は、単に争いを増長させる感情的な言葉であってはならない。相手に「礼」を説き、道理を諭(さと)して、冷静になることを促(うなが)す言葉でなければならない。その為には、口先で言い争う感情的な言葉でなく、冷静さを失わぬ言葉でなければならない。また、謝って済むならば、出来るだけ頭を低くして謝れ。意地を張らずに、相手に折れて謝ることも、護身術の一つだろう。
自分一人が逃げれば済む場合は、意地を張らず、努めて逃げよ。普段から、逃げ足の早さだけは鍛えておけ。
そして、まず相手にならぬことを第一とせよ。逃げられる時は、出来るだけ逃げられるように努めよ。それで自分が負けたことにはならない。
どうしても逃げられぬ場合や、相手にならなくなった場合は、状況把握をして、覚悟を決めて立ち向かえ。自分の連れに弱い者が居た場合は、決して弱い者を見捨てるな。
覚悟の上で戦わねばならなくなった時は、事の推移や、事情を証明してくれる証人を作れ。一対一の場合、相手が素手である場合は、道具や武器は使うな。
相手が多勢に無勢である場合は、道具や武器を使うことを躊躇(ためら)うな。但し、重傷を負わせぬ程度の努力は、最後まで捨てるな。こうなった場合、目的は相手側の戦意を失わさせるのが、第一の目的であることを忘れるな。そして“いざ”となったら捨て身になれ。自分の損得を勘定に入れるな。 |
|
8
|
卑怯な振る舞いをするな。恥辱(ちじょく)に対する感覚に強くなれ。
「恥知らず」な、礼儀に欠ける行為はするべきでない。同時に、「敬礼」の意味を理解せよ。「礼」はお辞儀のことではない。また、返礼でもない。
「礼」は本来《屈体(くったい)の礼》に発する。その内容は、「拝(はい)」と「揖(ゆう)」である。敬礼作法の大事を知れ。これを知れば、卑怯な振る舞いはするまい。礼儀と言う「物差し」で、計ればなり事も失敗することはあるまい。 |