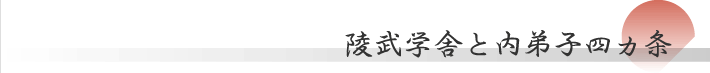|
●厳しい苦難と、乗り越えた後の恩恵としての名誉
「風雪に堪(た)える」と言う、古くからの言葉がある。
風雪とは、きびしい苦難を現す。極限まで堪え、風と共にふる雪を凌ぐと言う意味を持つ。
内弟子の修行とは、まさにこうした事を言う。
人知れず黙々と修行に励み、目立たぬところで地味な稽古を行う。これこそが内弟子に与えられた研究課題であり、これをどのように克服して行くかは内弟子自身の、これまでの人間性と、物事に対する思考力に賭(か)かっている。
しかし、内弟子の修行は生易しいものではない。地道に、過酷(かこく)な稽古に耐え、精神的にも肉体的にも、「陰徳(いんとく)」を積む修行に似ている。
では、陰徳とは何か。
陰徳とは、人に知れないように陰(かげ)で施す恩徳のことであり、恩徳とは人情に機微(きび)を知る、人への情けを体得する事である。
昨今は、世の中が殺伐とし、人倫が乱れて妻子ある大人の不倫が大流行であり、一方、不穏な事件や、通り魔殺人などの、血腥(ちなまぐ)い事件が目立つようになってきた。これは現代人が、拝金主義や金銭至上主義に、色も絡んで、未(いま)だ、踊らされていると言う事を明白に物語っているからである。
人間の価値観も、精神的支柱である心から離れ、金・物・色の物質的な欲望を募らせ、偏(ひとえ)に、こうした価値観は人の情(じょう/事象に感じて起る、主観的な知情意)から、金や物へと移行している現実があるからだ。
一説によれば、現代は心の時代で、拝金主義は終焉(しゅうえん)を迎えたと言われる。二十一世紀は心の時代であるとも、豪語される。
しかし、二十一世紀が心の時代であるとは言い難く、現実問題として、人の命や、人権は、未だ金銭に換算され、損害賠償などを含む民事訴訟で、生命ならびに基本的人権は、金銭に換算され、この価値観によって、人間の評価はなされている。
戦後の日本人の多くは、アメリカの持ち込んだ民主主義(【註】この主義はアメリカ国家が行う、国民への民族主義教育。その象徴が『星条旗よ永遠なれ』という、この国の国歌だ)の真の姿も知り得ず、異口同音にして入れ揚げ、手放しで喜んでいるが、ここに民主主義と資本主義の交錯する箇所に、大きな落とし穴がある事に気付いていない。
私たち日本人が戦後民主主義教育の中で、安易に信じ込まされたのは、アメリカと言う国家が平等社会を標榜(ひょうぼう)しているのにも関わらず、その裏側にある、アメリカのタブー(【註】実はアメリカは階級社会。しかしこれを公表することは禁忌)を排除した、「平等」という神話に魅せられ、これに入れ揚げた事でなかったか。
しかし、アメリカのもう一つに顔は、途方もなく複雑な現代社会に、歴然と階級制度が実在することを見せつける現実である。例えば、人が何かを考えたり、行動する時、この国では、「階級」(クラス)と「自分の出身母体」(祖父母までに遡る家柄あるいは出身大学の倶楽部)が考慮されると言う現実だ。
アメリカと言う国の本当の素性を知らない多くの日本人は、民主主義の本家であるこの国に、階級など存在しないと思い込んでいる。しかし、アメリカこそ階級社会であり、平等を標榜する民主主義は、実は平等など何処にも存在していない事が分かる。そしてアメリカ社会を広く見回してみると、階級問題は霧に包まれて、いつも複雑で、微妙な問題が横たわっている事が分かる。
ところが多くの日本人は、この現実を知る事はない。
アメリカを表して、「階級社会」等と言うと、不快な嫌疑が掛けられ、その分析に熱中したり、研究したりすると、忽(たちま)ちのうちに権威筋から精神異常者か、つむじ曲がりの異端視扱いされるようだ。
しかし、「平等」というアメリカの神話を安易に信じる日本人は少なくない。そして何処までも、神話を神話として存続させようとする、岩波書店を中心とする進歩的文化人の権威筋の企みがある。
平等でない現実を、平等の言葉に置き換えるところに、今日の民主主義の説く安易な平等観がある。だが、この平等観こそ、“平等過敏症”の自覚症状であり、世襲の肩書きや、地位、称号などと言った、便利な制度を持ち合わせないアメリカでは、各々の世代によって階級のヒエラルキーが規定され、これを主軸にして、「成功すること」に向けて、この国は動いている。「成功すること」が、この国では、決定的な重要性を持っているのである。
そして日本人の多くの若者も、こうしたアメリカ社会観に追随する思考が強いようだ。
アメリカ人の彼等が、社会生活を営む上での必要不可欠な事柄は、「人々の尊敬を勝ち取ること」である。
日本でもこの傾向が強くなり、タレントや芸能人までもが、尊敬に値する成功者として、脚光を浴びるようになった。スポーツ・タレントも同様だ。
しかし、アメリカの「成功すること」に、人生設計を置けば、尊敬されて、誰もが一廉(ひとかど)の人物の国と言うのは、日本も含めて、裏を返せば、誰一人、重要人物ではないという事でもある。
日本でもアメリカでも、努力すれば容易(たやす)く上の階級に伸(の)し上がる事が出来、金持ちになれると言う神話がある。この神話など、取るに足らないと軽く考えたところで、現実問題としては日本でもアメリカでも、歴然として階級制度があり、階級制度の現実の罠(わな)に嵌(はま)った時、下から上へ登る人生の登攀者(とうはん‐しゃ)は、苦々しさと、幻滅と言うものの洗礼を受けることは必定である。
資本主義と程よく合体し、国家規模の「ねずみ講」を奨励する民主主義は、グローバル的な平等の背後に宿し、相続財産、幼児期の生活環境、自身の出身大学の学閥、父母の出身母体や家柄・階級といったものが不条理に明らかにされ、これが社会的階級の階段を駆け登る条件となっているのは、明白な事実である。
「階級のない社会」という、タテマエ論としての神話は、幻滅のうちに最早(もはや)崩れ去っているのである。そして「階級のねたみ」は、時として、いざとなれば復讐(ふくしゅう)の為の平等主義に拍車を掛けるのである。
私たち日本人は、アメリカ社会同様、平等主義と民主主義を区別して考え、「市民は公平に競争をする」という競争原理の中に於てのみ、拝金主義に固まって生息している微生物なのであり、また、ひと握りのエリートも、庶民を顕微鏡下の微生物扱いして、何の憚(はばか)ることもない。
戦後の教育を受けた多くの日本人は、とにかく民主主義、さしずめ平等主義には、ひときわ入れ揚げるところが多かった。民主主義や平等主義の実態を解することもなく、一方に於いて、右翼だ、左翼だのと、権力中枢形態の本質も見抜くことが出来ず、唯物行為や経済万能主義に入れ揚げ、拝金主義の真っ只中にあって、金や物や色に踊らされてきた。
そしてこうした現実は、今も依然として続けられている。
こうした現実の中で、身を窶(やつ)し、年老いて、ボロ雑巾のように捨てられる人生観が果たして、掛け替えのある人生を全うできるか否か、甚(はなは)だ疑問である。
尚道館ではこうした現実の反省から、若者に対し、あるいは日本の青年として、意義ある、有意義な、悔いのない人生を体得してもらいたいと言う祈念を掲げ、独自な指導方法をもって、後進の指導者となる為の、西郷派大東流合気武術の指導を行っているのである。
しかし、これまで多くの若者が尚道館の内弟子制度の門を叩き、途中で挫折し、無慙(むざん)に故郷へと引き下がって行った。そして未(いま)だ、一人も我が西郷派大東流合気武術の、内弟子修行を遂行した者は居ない。
しかしそうした中、この度も、十年ぶりに内弟子を志す若者が、尚道館の門を叩き、内弟子として入門した。
人間の修行とは頭で考える程、生易しいものではない。
「修行」は思考で理解できるようなものではない。自分の霊肉共に極限まで追いやり、その限界を見極めると言うのが修行の真の姿であり、その見極めが出来た者だけが、晴れて新たな人生の第一歩を踏み出す事が出来るのである。
これまでの挫折者の多くは、自分を棚に上げ、自らの極限追求に敗れた事を、他人の性に責任転換し、自分は正しかったと言い張るものが少なくない。
しかし彼等の共通した意識は、現代社会の甘やかされた現実に、便利さと快適さと、更には豊かさだけを享受(きょうじゅ)すると言う意識が身に付いて、自らを苦しめ、その極限に向かって、難解な西郷派大東流合気武術の真髄に触れる事の出来なかった者達である。
他を中傷誹謗し、自分を棚に揚げて、自らを顧みないのは概ねの人間の常である。並み以下の人間はこれに含まれ、多くは凡夫に等しい。しかし凡夫でありながら、凡夫の域から脱出しようと企てる人間の気持ちは、実に美しく、貴く、清々しいものがある。凡夫に甘んじる事なく、少しでも自分を向上させ、人格ならびに品格を高め、霊格までもを高めようと日々努力する人間の姿は、実に美しき限りである。
そして内弟子の一日の始まりは、『陵武学舎・内弟子四カ条』の斉唱から始まる。
陵武学舎の精神は、「まこと」であり、陽明学の云う「まごころ」である。「まごころ」とは、偽りのない心を顕わし、「誠の心」を意味する。「誠の心」は、「赤心(せきしん)」であり、「真実の心」を指す。
『後漢書光武紀』には、「赤心を推して、人の腹中に置く」とあり、「まごころを以て、人に接し、少しもへだてをおかないこと」と教示され、人を信じて疑わないことこそ、「赤心」という「まごころ」の第一義と説いている。つまり「赤誠」である。
陵武学舎は「内弟子四カ条」をもって、人間教育の本義に帰るが、その奥に座するものは、心と心を師弟共にぶつけ合う信義であり、「信」の一字に賭けて、「誠意」を主張するのである。

●内弟子の行事は、まず断髪式から
内弟子入門者は、まず「剃髪」という厳粛(げんしゅく)な儀式を受ける為に、何人たりとも剃髪を行い、謙虚さと忠節の証(あかし)として尚道館では「断髪式」が行われる。
昨今は、ヘアー・ファッションなどが巷(ちまた)で流行し、茶髪や長髪と言った髪型が、スタイリストや仕掛人によって仕掛けられているが、尚道館の内弟子はこうした世間の流行とは一切無関係である。
尚道館・陵武学舎の内弟子の剃髪は、古くは「山嵐」で有名な西郷四郎の剃髪に由来する。
西郷四郎は生涯剃髪を通した人物として知られるが、その真意は、武術家の「忠節」を顕わしたものである。
坊主頭は、何も修行者に課せられた「忠節」の意味を持つものだけではなかった。江戸時代は、僧侶とならんで、医者も坊主だったのだ。医者の坊主は、忠節を尽くす人間の証で、「まごころ」をもって人々を治すと言う意味が込められていた。それが「医は仁術」と言われた所以だ。
こうした思想は武術家にもあり、かつては柔術の道場などが、骨接ぎなどで地域の人々の地域医療に貢献していたのである。そして坊主頭の柔術家も少なくなかった。天神真楊流柔術の「名倉堂」はこうした、当時の地域医療に従事した医術で有名だった。
ところが西洋化の波が日本に押し寄せ、髪の毛を伸し始めたのは、明治維新以降の事であり、それ以前は「まごころ」の証として、柔術家は坊主頭が普通だった。発足当時の講道館でも、坊主頭の修行者が多かった。
曽川和翁宗家の著書『旅の衣』(後編)には、「剃髪」について、次のような興味深い一節が書かれている。
「この印伝式は、他の段位等の印可式と異なり、正式に道統を伝承したという証(あかし)に、それを伝授する方も、それを授かる方も、一点の曇りもないという相伝の証に、双方は頭を剃髪(ていはつ)し、後世までそれを伝えていくことを互いに確認し、授かった方はそれを誓うのである。私が頭を丸め、剃刀(かみそり)で頭髪を剃り落とすことは、大学二年のとき以来であった。
剃髪をして、山村師範と対面した時、微かな戦慄(せんりつ)と緊張が趨(はし)った。
そして賜わり物を手にした時、当主二代(第二代宗家)としての、その責任の重さと、大変なものを継がされてしまったという、一種の小さな後悔と、この流派の看板を一生背負っていくことの重荷が感じられた。
その意味で私は所詮(しょせん)道統を継ぐような器ではなかったのかも知れない。
私に山村師範が道統を継がせたのは「何故だろう」と、今でも考えることがある。
その道統を継いだ重みは、頭髪を剃り落とした頭の軽さと反比例して、大きな責任に喘いでいるようであった。
密教や古神道の秘伝形式で道統を伝え、印伝式を行う流派は必ずといっていい程、その儀式に際して剃髪を行う」と、出ている。
剃髪は、「まごころ」の証を表現する人間の行動原理である。
ところがファッションにこだわる現代の多くの若者は、剃髪することを潔(いさぎ)よしとしない。心の中身より、外側の、どうでもいいような、外形のみにこだわって、そこに愚かな価値観を外見に求めようとする。しかし、こうした、外見にこだわる人種に、内弟子の厳格な修行は出来るはずがないのである。
尚道館の内弟子の第一歩は、自らを律し、素直な心をもって、内弟子としての「まごころ」を表現することなのである。
では、ここで内弟子の一年について紹介してみよう。
内弟子の一年の生活は、月毎に次ぎのような行事を遂行して行くことになっている。特に、二月に行われる、「大寒稽古」は、内弟子殺しの異名をとる程、凄まじいものだ。「大寒稽古」では内弟子同士が、お互に水盃(みずさかずき)を交わして過酷な稽古に入るのだ。
| |
陵 武 学 舎 月 毎 の 行 事
|
|
1月
|
2日の初稽古。中旬の鏡開き。大寒稽古に備えての特訓開始。 |
|
2月
|
内弟子殺しの異名を取る「大寒稽古」。一番、寒のきつい10日から28日まで。午前三時、冷水を被って稽古に入る。かつては衝撃で心臓マヒで救急車で運ばれる者も居た。 |
|
3月
|
道場内の半自給自足の菜園造り。畑の耕作や山からの土取り。薯類の苗の植えつけ。 |
|
4月
|
夏野菜の苗の植えつけ。そしてその後、一輪車で近くの川から水をバケツに汲んで来て、過酷な水遣りが始まる。この作業は、一日も欠かせないのだ。足腰の鍛練にもなる。 |
|
5月
|
半自給自足の為、野草の収穫。山稽古の折、食べられる物と、そうでない物の識別法を教わり、太陽光線を一杯に浴びたエネルギー豊富な野草を持ち帰り、調理する。 |
|
6月
|
前期・修得検定試験。成績は優・良・可・不可の4ランクで判定され、不可は追試がある。これまで口述筆記したり、儀法指導を受けた内容から問題が出される。 |
|
7月
|
各地の地域講習会への出稽古。暑中稽古開始。 |
|
8月
|
夏季合宿セミナー。10日〜15日。全国から門人や部外者の武道修行者が集まる。年に一回、古い仲間と顔を合わすのもこの夏季合宿セミナーである。 |
|
9月
|
冬野菜の苗の植えつけ。季節は、この時期を境に、急速に秋が深まって行く。暑かった夏は23日で峠を超え、この日を境に秋へ、そして冬へ。 |
|
10月
|
各地の地域講習会への出稽古。尚道館が主催する講習会に、宗家と伴に出向く。茨城・千葉の各講習会もこの時期に行われる。宗家の御供をして、講習会や出稽古に向かう傍ら、「三寸さがって師の影踏まず」を実地で学ぶのだ。 |
|
11月
|
野外実戦・山稽古月間。山河の地形を利用した戦略と戦術を学ぶ。 |
|
12月
|
冬稽古に備えての寒稽古開始。後期・修得検定試験。これまでの一年間の修行の成果をまとめあげた小論文提出。追試があるのは前期試験と同じ。 |
●内弟子は、まず徹底的に「礼儀」と「歩き方」と「言葉使い」を叩き込まれる
尚道館・陵武学舎で先ず最初に教えられるのは、「礼儀」である。昨今は礼儀知らずの人間が多くなり、これは何も若者や弱年者だけとは限らない。いい年をした大人も、老人に至っても、子供の頃からの幼児趣味が脱けきらず、礼儀知らずの大人は実に多い。
礼儀とは、読んで字の如く「礼」と「儀」のことである。
「礼」とは、社会の秩序を保つ為の生活規範の総称であり、「儀」とは、行動規範を顕(あら)わし、進退動作の上で手本とすべきものである。
つまり「人の行うべき礼の道」のことを言う。そしてこの裏には、社会生活の秩序を保つ為に、人が守るべき行動様式が含まれている。
また一方、特に、敬意をあらわす作法を、礼儀は顕(あら)わす。更に、礼儀を尽くす人間程、格が高いと言うことになる。
拝金主義の世の中では、金持や、裸一貫から成り上がった成金主義者は英雄のように扱われ、羨望(せんぼう)と尊敬の的になるが、そんなものは大して自慢にはならない。物財的財産より、武士道実践者は精神的財産を重んじる。
多くの人間は、自分の財産目録に入れるような事柄を挙げる場合、金や物以外あげるものが殆ど、何もない。しかし、武士道実践者は、自分の財産目録に、「礼儀」を入れ、これまで培った「教養」を入れることができる。人間は、この二つが欠けていれば、人生の深みを感じ取ることは出来ず、無規範な行動原理しか取れなくなる。「礼」と「儀」を知らない為だ。
宇宙の進退ならびにその運行は、天文や地理の理(ことわり)に則して行われている。
各種法則も、その根元は秩序ある運行によって、整然と行われているのである。則(のっと)るべき法則があってそれが規範となり、判断され、また、評価される行為があって、それが人間の行うべき行動学の拠(よ)り所となる。こうした行動学を知ることこそ、自らの財産として自慢すべき精神的な財産目録であり、決して物財のみが財産目録ではないのだ。
また「歩き方」に於いても、同様の事が言える。
歩き方は礼儀の一種であり、進退行動の要(かなめ)である。粗雑で、がさつな人間は、歩き方がだらしなく、街を闊歩(かっぽ)するにも我が物顔である。肩で風切るような横柄な歩き方は、自分一人でいい気になっていても、他人の眼からは見苦しく映り、決して自慢できるものではない。自覚症状が現れ無いことこそ、惨めなものはない。更に、進退動作に於いて、こうした無態(ぶざま)な態度こそ愚かなものはないのだ。
一廉(ひとかど)の人物か、そうでないかは、歩き方を一目見ればその中身は総て分かるものである。進退動作の行動原理に則していない者は、幾ら良い服に身を包み、高級な靴を履き、高価な装飾品で身を飾っていても、その中身が不完全な為、そうした仕種(しぐさ)だけで、他の敵意ある人間から羨望(せんぼう)や怨みを買い、最後には命を付け狙われることになる。暴力団組長や幹部が、街角で狙われて命を落とすのは、こうした行動原理の大事を知らないからだ。
本当に強い人間は、その行動が実に穩やかである。歩き方一つにしても静かである。
昔の、儀法に精通した達人は跫音(あしおと)を立てて歩くようなことはなかった。つまり「歩行」こそ、日常動作で頻用(ひんよう/繰り返し用いられること)されるものである。
したがって幾ら用心しても用心し過ぎることはないし、修行も、それで終わりと言うところはない。修行の原点や行動原理の根本は、「歩き方」にあると言える。
また歩き方は「姿勢の良し悪し」に繋(つな)がり、姿勢を正しく保つと同時に、跫音や膝を柔らかく保ち、躰(からだ)の動揺をできるだけ少なくして、重心軸を安定させる。
かつて、跫音を立てて歩くような武術修行者は、その実力の程を疑われた。また、嗜(たしな)みの欠如と軽蔑された。
跫音を立てて歩くような人間や、足の踵(かかと)を引き摺って歩くような人間は、その歩行途中、人や物に接触したり、躓(つまづ)いて顛倒(てんとう)する条件が多くなる。したがって武人に課せられた命題は、跫音を立てず、極めて静かに、進退する行動規範が求められた。跫音を響かせたり、沓(くつ/鹿皮で出来た乗馬用のくつ)や履物の踵を引き摺って闊歩するような者は、武術の修行中にあるまじき行為と軽蔑され、不用心と不用意と神経の粗雑さを物語る輩(やから)として、決して高い評価はされなかったのである。
古人の唱えた、「虎視牛行(こし‐ぎゅうこう)」を見習って、虎のように辺りを鋭く観察し、牛のように悠然(ゆうぜん)と歩く修行に徹したいものである。
次に厳しく指摘され、徹底的にこれまでの習慣を改造されることが「言葉使い」である。
昨今は、尊敬語や丁寧語、更には敬語が入り乱れ、奇妙な日本語が巷では大流行している。
また、昔は「男の一言」というのがあって、「言葉は重く用いよ」という戒めがあった。しかし昨今では、自分の発した言葉に重きを置かず、途中で覆して、日本古来の言霊を乱す愚かな現象が巷には溢れている。
そして老若男女を含めて、正しい言霊など、遣われている気配は殆ど感じなくなった。とにかく言葉は欧米外国語と和製英語が相まって、極めて乱れているのである。しいてはこの乱れは、正しい宇宙の波動すらも狂わせてしまう、大きな危惧の原因になっている。
言葉について、「言葉」の持つ意味は、宇宙波動からすれば「光透波(ことば)」であり、光透波は正しい「言葉使い」の波動から起る。言葉を正しく使う事によって、言霊は正しく作用し、本来言霊は、全人格をかけて使うべきものなのである。したがって吐く言葉には、重きが求められ、軽きが軽蔑されるのである。
故事には、自分の吐いた一言を守り、信義を貫こうとして一命を落とした人物の話がよく挙げられている。
特に、魏徴(ぎちょう/唐初の功臣で、隋末の群雄の一人李密、唐高祖の太子李建成の臣を経て、太宗に仕えてよく諫めた人物)の詩の『述懐』には、「季布(きふ)に二諾(にだく)無く、侯贏(こうえい)一言を重んず」とあり、侯贏は『史記』(合計130巻からなる前漢の司馬遷の著書)に登場する人傑の人物であるが、「一言承知した」と口から吐いた言葉を、全うしようとして信義を貫いた人物として知られている。
これは「君子に二諾無く、志士(しし)一言を重んず」という信義遂行者に通じ、後に格言(【註】深い経験を踏まえ、簡潔に表現したいましめの言葉)として日本でも「男の一言、重きこと千鈞」などの諺(ことわざ)が生まれた。
そして、言葉使いは正しさとともに、古来より我が国の武人は、本心に無いことを言ったり、自分の吐いた言葉を途中で撤回して実行しなかったり、己を偽る態度をした場合、こうした輩(やから)は悉々(ことごと)く軽蔑されたのである。
したがって人が肚(はら)を割って話す場合、こうした態度から、真実を歪曲(わいきょく)したり、遊離したりのタテマエ論などは出てくるはずがないし、その入り込む余地もない。
ホンネとタテマエが、別々の形で出され、遊離した考え方で人間の言葉が乱されて久しいが、それだけで総体的に見た場合、人間の品格が、一層卑(いや)しくなったと言えるであろう。
嘘を吐いても、それに責任を取らないのが、タテマエとホンネを上手に使い分ける現代人特有の小賢しさだが、ホンネを卑しいままに放置したところに、そもそもの人格と品格の欠如がある。
現代人の特徴の一つに、ウケのよさから小賢しいタテマエ論をぶち、立派そうな言葉の言葉並べをするのが流行のようになっているようだが、これを躊躇(ためら)わずに使っている者は、自ら自身の全人格を否定し、卑しめていることになる。
言葉に、「よそゆき」の言葉とか、「うちわ」の言葉とかは存在しない。表裏のない、一貫した言葉使いこそ、武人の学ぶべき修行の大事は、二言のない、一貫した態度で貫く姿こそ、武人に課せられた使命である。
人生は何事につけても、しくじり易いような構造をしている。心遣いの疎いものは不埒者(ふらち‐もの)と叱責(しっせき)を受け、「不届きでした」とか「行き届きませんでした」と、後で詫びてみても、「覆水(ふくすい)盆に返らず」である。
尚道館・陵武学舎では、将来指導者として、あるいは道場開業者として、世に送出す内弟子に対し、こうした早期から徹底した言葉使いを指導するのである。

|