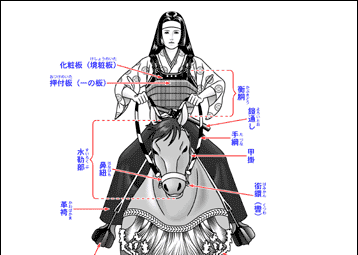 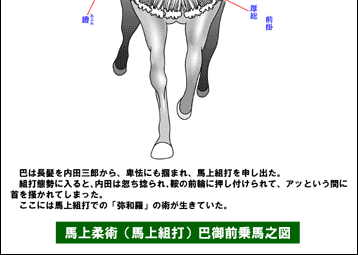 |
| さて、巴御前(生没年未詳)は木曾の豪族中原兼遠の娘である。そして今井兼平の妹でもある。この武勇に優れた血縁の血筋は大きい。 幼少より、武勇すぐれた美女の誉れ高く、源義仲に嫁し、武将として最後まで随従した。夫の戦死後は和田義盛に再嫁し、その敗死後、尼となって越中に赴いたという。また一方において、「耶和良之術」の達人でもあったと言う。 巴御前の今日に伝わる様々な逸話は、多くは巴が生きた時代背景と無縁ではなく、戦場の戦い振りにおいて、様々な逸話が生まれた。 平安末期から鎌倉初期において、馬上から敵を引き摺り降ろし、あるいは前輪に敵の頭部を押さえ付けて打ち取る術は「耶和良之術」として記されている。 これによれば「徒歩武者、我に組み付きたる時は、馬を駈けさせて引きずり、打ち取るべし」と記され、また「騎士を打ち取るべき時機は、前輪に兜を押し付けたまま、打ち取るべし」とある。 こうした技術は後世に至って柔術の「抜手術」として発達するが、既に源平組打時代においてもしばしば戦場で用いられており、組打において一方の者が短刀を抜いて一方を突こうとする時、一方はその小手を掴むものである。そして一方はそれを外し、さらにこれを掴もうとする。 これが「抜手」であり「外し手」であった。 しかし相手の腕を掴んで引きずる事は上級の武士では普通出来ない事である。この敵を引きずる術は、よほど馬術が上手でなければできる事ではなく、呼吸を誤ると忽ち敵に我が馬の尻に飛び乗られてしまい藪蛇となってしまうのである。敵を引きずるには敵の袖を掴み、同時に我が馬に飛び乗られないように敵を突き放していなければならない。更に迅速に短刀を抜いて敵の急所に止めを刺す事が主眼になり、こうしたものを「耶和良之術」といったのである。 |