■ 壮年ならびに高齢者のクラス■
(そうねんならびにこうれいしゃのくらす)
●自分の復活を目指して
前向きな人のことを、でしゃばりといい、身の程知らずと罵声の批難がかかる。現代は、こういう時代ではないのか。
ここに現代の科学万能時代の本性と言うものが、見えてきたような気がする。
ライブドアも、村上ファンドも、こうした「前向きな人」に対して悪の烙印(らくいん)を押し、マスコミが「平等」の美名の下(もと)で摘み取った、一種の捏造(ねつぞう)騒動であったということが分かるだろう。
日本は、デモクラシーの名を借りて、不可解な圧力のかかる「前近代的な社会」である。
「出る杭(くい)は打たれる」の喩(たと)えから、とにかく出る人は、打たれ、摘み取られ、悪として摘発され、一様に平均化されてしまうのである。そしてこの社会では、これを「平等」という。
何と、これは押し付けがましい傲慢(ごうまん)な論理ではあるまいか。
この論理をもって、一個人でも、悪意の眼で見ると次のようになる。
温和な人を女々しいという。
勇敢な人を乱暴者という。
思慮深い人を決断力のない人という。
純朴な人を田舎者という。
無垢な人をお人好しという。
万事に丁寧(ていねい)な人を鈍間(のろま)という。
総て現代は、こうした悪意の眼で動いている社会でもある。
そして現代という時代は、精神世界が栄えた時代が遠い過去のものと忘れ去られ、物質最優先の、物質至上主義が持て囃(はや)されている。
こうした社会にあっては、リストラを迫られ辞職を余儀なくされている人、破産に追い込まれる人、借金取りに追われて逃げまくっている人、家庭が崩壊している人、警察や検察の追及を恐れている人らは、窮地の崖っぷちに立たされているのも同様であり、それらの人の耳に聞こえるのは、おそらく死神の囁(ささや)きだけであろう。
人間は、同じ心の中で感得する様々な現象も、気持ちの取り入れ方が狂えば、このように、困窮する心に左右されてしまうのである。
心は、好きなことをしている時は、さほど疲れない。仕事もで、運動でも、自分の性(しょう)に合っていることをしている時は、疲れても、いい気持ちで疲れているので、その疲れは、かえって健康増進の為に役立つ。
しかし、やりたくないことをしている時は、直ぐに疲れが出る。仕事でも、やりたくない仕事は、直ぐに疲れ、肩が凝り、胃が痛くなる。つい愚痴も出てきて、溜息が出る。欠伸(あくび)も出てこよう。こんな仕事など、辞めてしまいたいと思う。厭々(いやいや)ながらの仕事は、やがて過労死を招く。
こうした根底には「心の働き」がある。心が関与して、愉快にさせたり、不満を齎(もたら)したりする。
現代人は、あまりにも物質的な豊かさや贅沢(ぜいたく)さ、快適さや便利さを追い求め過ぎた結果、「人間の心」の働きを見失ってしまった時代の真っ只中にいる。ここに病む現代の側面がある。
自分を見失えば、自分の心が分からなくなる。混乱を来たす。そこに心身相関病の病巣がある。生活習慣病の病因がある。この事によって、精神も病む。頭も血液も汚染する。
心の働きを知らないから、気の働きというものも分からなくなる。気の働きが分からなければ、気が病み、これが病気へと変質する。現代病の多くは、これが元凶となっている。その元凶が、心身相関病であり、生活習慣病ではなかったか。
さて、現代人こそ、「心とは何か」ということを探求しなければならない。しかし、それに向かって、精神統一をしたり、精神の集中と称して、これに励んでみても、何の役にも立たない。むしろ力まずに、自然のままに任せて、自然に則した生活の中で、自分の心を見詰め直す必要がある。
誰にでもある力を、静かに想い、その自然のままで、自分を見詰め直す作業を丹念に行えば、既に忘れてしまっていた、自分の心を復活させることが出来るのである。置き忘れた自分の心に目覚めるのである。
その復活に対し、わが西郷派大東流は、自分の心の復活を目指す壮年層に、新たな活力を与える手助けをしているのである。
●人生の折り返し点を過ぎ、熟成の歳に至ったとき、人は何をすればよいか
人間は長生きしても、せいぜい、百年ほどの人生である。
多くの人間は百年も経たないうちに、その殆どが死に絶えてしまう。また、運良く百の長寿まで生きられたとしても、その多くは、寝たっきり老人であったり、植物人間であったりして、生命維持装置の厄介になり、薬漬けにされて、辛うじて生命だけを繋(つな)いでいるだけの「生きる屍(しかばね)」である。
その殆どは、生きる屍の域を出ない。自分で喋ることも、歩くことも、考えることも、働く出来ない。ただの、生物の形態を成している物体に過ぎない。人格を持たない物体である。行動を伴わない点では、動物以下の姿に成り下がっている。もはや寝たっきり老人に、人としての尊厳はない。
そこで「人生とは何か」ということを、真剣の模索しなければならない。人間は、人生の折り返し点を過ぎたら、改めてこの事を考えなければならない。誇りある壮年期を迎え、名誉ある晩年期へと繋(つな)げなければならない。
しかし、現代という時代は、こうした生き方が困難な時代でもある。
現世と言う「この世」は、あらゆるものが複雑に、複合的に組み合わされて、依存しながら存在している。何一つ、単独で動いているものはない。しかし、現世は現象界であり、私たちの棲(すむ)む現象人間界は、変化し、流転(るてん)するという制約に縛られている。その為に、固定した実体というものが、何一つない。
ところが人間は言葉を用いて、現象のそれぞれに名称や名前をつけた。自分の足許(あしもと)を見て、踏みしめたものを「大地」といい、天を指して「空」と名づけた。そして自分にも、「わたし」もしくは「ぼく」という一人称での呼称をつけた。
こうして、一旦名前が与えられると、大地も空も固定した、実体を持つ存在に思えてくる。かくして、私たち人間は、固定観念の世界に絡(から)め捕られ、先入観に襲われるのである。
大空を見上げて、何処から何処までが空か、判然としない。また、大地を見て、山や丘の判別がつくだろうか。
こうして人間は、言葉や固定観念に囚(とら)われ、この中に絡め捕られていく。その為に、人間は「こだわり」を、「わたし」や「ぼく」に向け、これに固執するようになる。そして遂には、あまりにも「わたし」や「ぼく」にこだわる為、自分が、年とともに老いて、死んでいく自分を案じ、この現象を「怖い」と思うようになる。これが「死への恐怖」である。
人の悲しみや、苦しみの根源には、「死への恐怖」が横たわっている。
しかし、無常は止(や)むことがない。変化をし続ける。現象界では、一時たりとも止まる事がない。常に流転(るてん)するのだ。
宇宙は絶えず、「生成」と「死」を繰り返している。その中に、現代を生きる私たちがいる。その中で形成されている以上、私たちの世界もいつかは破壊され、やがて「空(くう)の世界」に回帰する。
変化は生成し、その後、必ず死が齎(もたら)される。この世に生まれ出た人間は、必ず死に向かって、一歩一歩、歩んで行かなければならない。
「自分はまだ若い」などと、箍(たが)を括(くく)ってはいられない。また、「死は、自分には、まだまだ先のことだ」と安心してもいられない。だから「死について考える」など、ナンセンスだと一蹴(いっしゅう)することも出来ないだろう。そうした隙(すき)にも、死は確実に忍び寄っている。
一般的に言って、「老化」は老人の問題のように考えられている。しかし、誰でも、生れ落ちたその日から、確実に加齢が始まっている。若者と雖(いえど)も、日々老化しているのである。若いといっても、病気に斃(たお)れれば、死の風に脅(おびや)かされる。
また、老衰が近づけば、やがて死を覚悟しなければならない。この世での「生」は、常に死の風に吹かれ、脅かされているのである。儚(はかな)いシャボン玉のような人の命は、いつ強風が吹いて、潰(つい)えるかも知れない。夜寝て、翌日の朝、元気に起床できるという保証はない。したがって、翌日の朝眼を覚ますことが出来るというのは、大変な奇跡でもある。
いつ、死の風に吹かれるか、それは何びと雖(いえど)も知ることができない。人間は奇跡の連続に頼っていかなければ、一秒たりとも生きることが出来ない。
一度、死の風が吹き始めれば、あなたがどんなに大富豪であっても、これを躱(かわ)す事は出来ない。家族や友人に恵まれたとしても、また、地位や権力を得ている人でも、一旦死の風が吹き始めれば、これらは何の力もない。金銭や財力で、どうこう出来ない。
したがって、人生の折り返し点を経験した晩年期は、自分の生きた証(あかし)を示す、ラスト・スパートであるともいえよう。それな、よく生きた人間だけに、「よりよき死」が与えられるのである。
「よりよき死」を迎える為に、あなたは一体何を模索しているであろうか。
年金生活を前にして、贅沢に送る老後を、後半人生のビジョンに描いているのであろうか。それとも、安穏とした後半の人生設計を、漠然と頭の中で描いているのだろうか。
しかし、あなたが目指す豊かな老後は、単に物質的な豊かさを指しているのではあるまいか。
多くの日本国民は、豊かな老後を送る為に、若い頃、懸命に働く。老後に備えて、働かないで喰っていく為に働く。つまり、最終目的は、働かない為に働く。これは、何と矛盾した考えであろうか。
しかし、誰も働かない為に働くという現実を、矛盾とは思わない。その自覚症状すらない。
そして、「働かない為に働く」という行為の中に熱中する。そして、これには老後の精神的な文化は、殆ど含まれていない。
ただ、誰もが豊かな老後を夢見ている。その豊かさとは、精神的な豊かさではなく、物質的な豊かさを追い求めているに過ぎない。それは精神生活が抜け落ちた「延命の老後」である。
あるいは、何処かの豪華マンションタイプの老人介護施設で、贅沢で、退屈な、気だるい日々に明け暮れる老後を夢見ているのであろうか。
 |
▲人生の折り返し点の後半から、また新たな精神世界を求める探求の余地が残されている。精神世界の蔑(ないがし)ろにした生き方では、決して「自分を知る」ことは出来ない。武術の教えるところは、修行を通じて「自分を知る」ことにある。
晩年を迎えた、あなたは自分が何者か、知り得たであろうか。この命題を解決できただろうか。 |
人間の生涯に、最終的な「有終の美」の時期があるとすれば、それは晩年期に差し掛かった時に思慮する「よりよき死の模索」ではないだろうか。
自分の生きた証(あかし)を誇り高く、名誉に導くものがあるとするならば、それは「老化する私」の現実を真摯(しんし)に受け止め、そのことを具体性をもって、これに関心を示すことではないだろうか。
現代を高齢化社会と位置づければ、高齢化は、一見長寿村のような意味合いを連想させるのであるが、何故か、「高齢化」と「長寿村」のイメージはイコールにはならない。暗い、惨めな衰退する社会を連想してしまう。これは何故だろうか。
それは日本人の平均寿命が延びた事にも起因していることであろう。しかし、平均寿命が延びたと豪語しても、それは薬漬けにされ、生命維持装置の手を借りてのことであり、健康的で、溌剌(はつらつ)とした老年期を過ごす老人が大勢いるということではない。
老年期にあっても、社会活動に参加し、意欲的に健康法を実践し、「日々新たに」の思想をもって、晩年期を元気に全うしている65歳の老人は、全体の一割にも満たないであろう。
それどころか、いま自分が若いと盲信している若年層にも、老化の魔の手は忍び寄っている。小学生の健康診断にも、糖尿病、肥満症、動脈硬化、高血圧、高脂血症、心機能低下などの成人病の兆候が現れ始め、また、思春期の憂鬱(ゆううつ)は、心を病み、鬱病や神経症を齎(もたら)し、精神を病んでいる現実は、何も老人だけとは限らなくなった。
そして、最も恐ろしいことは、現代の環境の変化に、子供のうちから老化が見られる現実がある一方、薬物や医療機器などの生命維持装置を使って、高齢者の平均寿命を押し上げ、国民の医療費に負担をかける現実があることだ。
薬物や医療機器などを使った高齢者の延命医療は、人体の自然の生理に反している。医療現場で実践されてるこうした医療措置は、単に高齢者をだらだらと生き延びさせておく、技術以上の何ものでもない。実に恐ろしい事といわねばならない。
また然(しか)も、生命維持装置によって、不健康に生き延びた老人達が、社会の尊敬を受け、生産現場に復帰して、精神的文化に大きな貢献をしているという話は、一度も聞いたことがない。現実の日本に、誇りある老年を送る為の社会条件や習慣といったものは、この国にはないのである。
現実問題としてあるのは、老人は嫌がられ、最後は完全看護の、高級マンション風の老人養護施設で過ごすという、体裁の良い「姥捨て山」があるだけである。
こうしたところに収容されて、果たして「よりよき死」が得られるだろうか。
●健康に生き、そして「よりよき死」を得るために
人は死に向かって生きている。生まれた以上は、必ず死ぬ。しかし、人の死は、人それぞれに、様々な死に方がある。そして、家族に見守られながら、静かに、穏やかに息を引き取るということは、現代では稀(まれ)になった。
その意味で、現代は「自分の死」すら、「自由に選択できなくなった時代」といえる。
死は一般に、「自然死」と「事故死」の二つに分けられる。
しかし、現代社会では、「自然死」は稀で、多くの人は「事故死」をする。特に現代人の特徴は、病院で生まれて、病院で死んでいく、生も死も病院である。
かつては「月」の満ち引きに応じて、生死(しょうじ)が決定されていたが、現代人には、殆ど無関係となってしまった。
自然死に関する文献を紐解(ひもど)くと、人が自然死で死んでいく場合、潮汐(ちょうせき)の関係に、古人は注目しており、「干潮にほんの僅か遅れて死がやってくる」と記されている。こうした古人の文献から窺(うかが)えることは、月は、潮汐を通して、人の死にかかわっていたことが、非常に高かったと思われる。つまり昔は、人間は月の波動に反応し、それに応呼していたことになる。
しかし、病院で生まれて、病院で死んでいく人生しか選択できない現代人は、かつての古代人のように、自然死として、潮が引くように死んでいく事は不可能になった時代だとも言える。
この意味からすれば、現代人は、古代人より遥(はる)かに退化した、「生」と「死」を生きるしかない味気のない人生に生きていることになる。
そして、特記すべき事は、「月が、死と不死を司る神として観念」されていて、月が人間の死を司っていたとしたら、一体これはどういう事になるのだろうか。
また、古人の文献によれば、「人間は潮が引くときに死ぬのだ」という伝承が残っており、一方、古代人の観察眼は鋭く、これがもし、真実としたら、病院で生まれて、病院で死んでいく現代人の、この人生は、一体なんなのだろうか。
私たち現代人は、太古の人や、人の死と、潮汐を関連付けた古人に対して、面目を失うほど、退化した人類と言えなくはないだろうか。
人間は、生れ落ちる過程で、生・老・病・死の四期(しき)が、必然的に人生として割り付けられる。人の死は、「生」の逆のコースを辿って死に向かうという。そして、「死」は咽喉(のど)の渇きから始まるといわれる。その際、「六つの中有(ちゅうう)と、三つの経験がある」といわれる。またこれは、東洋医学の思想の中にも見られる。
古い東洋医学の文献(【註】『霊枢』邪客篇)を紐解くと、「人は天地と相応ずる」とある。
つまり天地の陰陽が、人間の体内にも現れているということである。これを総じて、人体を「小宇宙」と定義しているのである。天体の大宇宙(大太極)に対して、人間はそれに応呼する小宇宙(小太極)なのだ。
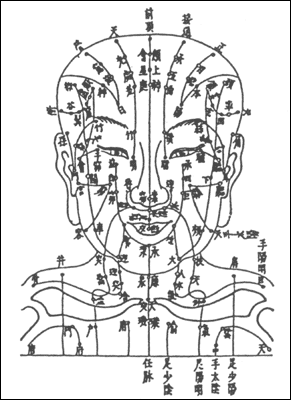 |
|
▲肉眼で確認できない気の経路の「経絡図」
(画像クリックで拡大)
|
手には、太陽小腸経(たいようしょうちょうけい)、少陽三焦経(しょうようさんしょうけい)、陽明大腸経(ようめいだいちょうけい)、太陰肺経(たいいんはいけい)、少陰心経(しょういんしんけい)、厥陰心包経(けついんしんぼうけい)があり、また、足には太陽膀胱経(たいようぼうこうけい)、少陽胆経(しょうようたんけい)、陽明胃経(ようめいいけい)、太陰脾経(たいいんひけい)、少陰腎経(しょういんじんけい)、厥陰肝経(けついんかんけい)の三陰三陽の、合計12経絡を教えている。
人間が生まれながらに持っている成長ならびに発育の根源は、「生命力」である。この生まれながらの気を「先天の気」という。また、生れ落ちた後、飲食や大気などから取り込まれる酸素などの天空の気と、「先天の気」を合わせたものを「後天の気」といい、「先天の気」と「後天の気」を合わせたものを「真気」といい、これが気の本質である。
人間は気の運行により、成長と発育の生命活動を営むことが出来る。この真気運行の通路が経絡であり、ここに12経絡と、奇経脈の任脈(にんみゃく)と督脈(とくみゃく)を合わせて「14経絡」となる。
そして、中有(ちゅうう)は、「三つの経験」をするといわれる。その三つの経験とは、「死の瞬間の中有」「死した後の表現形態の中有」「再生を求めて父母を探す中有」の三つであり、この三つの経験は、「生」とは、逆のコースを辿って行われるという。
東洋医学ではこの「三つの経験」を、次のように定義している。
「上焦(じょうしょう)」を横隔膜(おうかくまく)より上とし、「中焦(ちゅうしょう)」を横隔膜から脾経の神闕(しんけつ)までとし、「下焦(かしょう)」を臍(へそ)から会陰(えいん)までとしている。
人が誕生する過程を追えば、それは「焦(しょう)」からはじまる。「焦」は火が燃えて、それが焦(こ)がす態(さま)を表す。
まず、生まれる瞬間は母体の陣痛(じんつう)に始まり、子宮から膣の産道を通って、外に押し出される。この時の胎児の意識は、膣を通って出て行く際、「鉄のトンネル」の如き産道を通って、外に押し出されるようなもので、言語に絶する苦痛であるという。その苦痛の為に、生まれ出た赤ん坊は、「鉄のトンネル」を通って出てきたのであるから、その摩擦で真っ赤な躰(からだ)となり、そして痛さを訴える為に、ただ泣くしかないという。赤ん坊の産声(うぶごえ)とは、痛さを訴える為の、抗議への泣き声だったのである。
「オギャー」と生まれて呼吸の「呼気」をし、これが上焦である。阿吽(あうん)の「阿」である。
次に臍(へそ)の緒が切られる。これが中焦である。下焦で大小便をし、この三つの経験が、人間の誕生のプロセスである。したがって、「死」は、この逆のプロセスを辿るという。
まず、自然死の場合、下焦の会陰(えいん)が閉じられ、生命力は中焦の神闕(しんけつ)を経由して、上焦へと至る。上焦に至って生命力は、泥丸(でいがん)部分の百会(ひゃくえ)のブラフマの蓋(ふた)が開き、この開き口から、生命体を成す霊魂は体外に出ると、東洋医学では論じている。その時に、最後の息を引き取るのが「吸気」であり、これが阿吽(あうん)の「吽」である。
人の誕生は、生命力の「火」が焦げ始めることからはじまる。逆に死は、この「火」が消える事をいう。精液という、「水」から生じた生命力は、「焦」の尽きるとき「末期(まつご)の水」を必要とする。
つまり、人間は、中有→水(精液)→焦→末期の水→中有というプロセス通りに再生を繰り返し、生まれ変わりをするのである。これを仏道では「輪廻転生」という。
一方、事故死の場合は、自然死のようなプロセスが辿れない。
特に、水死や交通事故死、自殺・他殺や病死の場合、ブラフマの開き口は開かない。これは有無を言わさず、急激に死が訪れる為である。突然に襲ってくる死は、肉体と霊魂が分離する十分な時間がない。突然に、衣服を剥(は)ぎ取られるような凄(すさ)まじい死が襲うのである。
頭部の泥丸部のブラフマが開かず、生命力の魂は、肛門と睾丸(あるいは女陰)との、ほぼ中央にある会陰(えいん)から、「陰」の総気(そうき)が洩れるようにして出てしまう。
ブラフマの開き口から出た、「陽」の生気霊は、陽の性質に基づき、昇天していく。一方、会陰から洩れ出た陰霊は、地中深くに沈下していき、その感応は地縛状態となって、その場所に永く止まる事になる。一般には不成仏霊や地縛霊などといわれるが、これが事故死の実態であり、事故死とは、則ち、「横死(おうし)」を指すのである。
多くの人は、大方このように生まれ来て、また役割を終われば、もと来た場所へと帰って行く。人間は生を受け、生・老・病・死の四期を辿り、再び、もとの世界に帰って行くのである。
こうして人の死を観(み)ると、人の死には「様々な死に方」があるといえよう。
したがって、「死ねば、これまでの意識もなくなり、総てはそれでお終い」と云うようにはいかないのである。現世の三次元現在界は物質界であり、生活の基本は、物質至上主義や科学一辺倒主義で、主に可視世界を指す。これが「この世」という「表」である。
そして、人間の住む世界は現象界であるので、現象とは「変化」を指し、同時に変化をする為には「二大対極」の相反するものが存在しなければならない。眼に見える光以外に、もっと細やかな、素粒子より小さな心を司るモノがある。しかし、現段階では発見されていない。
この二大対極の向こう側に、肉の眼では確認できない「不可視世界」がある。これが「あの世」であり、「裏」である。
この事から人間の生命は、不可視世界と可視世界を循環していることになる。「生」あるものは、やがて寿命が尽きて「死」に至る。しかし、同じ死でも、様々な死に方があるのが周知の通りである。それならば、誰が考えても、事故死よりは自然死の方がいい筈(はず)である。死に態(ざま)にもレベルがある。
したがって、よりよき「死に態」を得る為には、生きているうちに「改心」しなければならない。
「改心」とは、単に、これまでの「行い」や「心」を改めたり、悪い心を教化することばかりを指すのではない。一般には「改心して、出直す」などというが、最初から、もう一度やり直すことばかりでなく、これまで間違った固定観念や、先入観を消去させることも「改心」の一つである。
間違った固定観念や、知らず知らずの間に蓄積した先入観は、固定的な観念や見解は、「自由な思考」を阻害する元凶となってる。真理が真理として捉(とら)えられなくなり、意図的な洗脳によって、先入観は固定化されてしまう。そこに自由を失う元凶が横たわっている。
例えば、先入観の一つとして、強い躰(からだ)と言うのは、「強靱(きょうじん)な肉体と、体力だけを指す」と考えている人が少なくないようだ。
また、「本当の健全」の意味も解しないまま、「健全な精神は、健全な肉体によって造られる」と思い込んで居る人が少なくないようだ。
あるいは強い肉体は、強い精神力を持ち、そこから強い力、強いエネルギーが放射されると信じて疑わない人が少なくないようだ。これこそが、間違いを誘引する、先入観と固定観念の最たるものではあるまいか。
|





